やなせたかし夫婦がアンパンマンにたどり着くまでの物語を描いた朝ドラ「あんぱん」。
あんぱん第16週「面白がって生きえ」では、東京で嵩が八木信之介と再会するシーンが描かれました。
八木は、孤児たちにゴーリキーの「どん底」を読み聞かせしており、嵩はそんな姿を見て「八木上等兵らしいな」と懐かしみます。
八木上等兵が読み聞かせしていた「どん底」とは一体どんなストーリーなのでしょうか?
そこで今回は、
- あんぱんに登場の「どん底」とはどんな話?
- 八木上等兵が「どん底」を読み聞かせした理由はなぜ?
について詳しく深掘りしていきます!
あんぱんに登場の「どん底」とはどんな話?あらすじは?
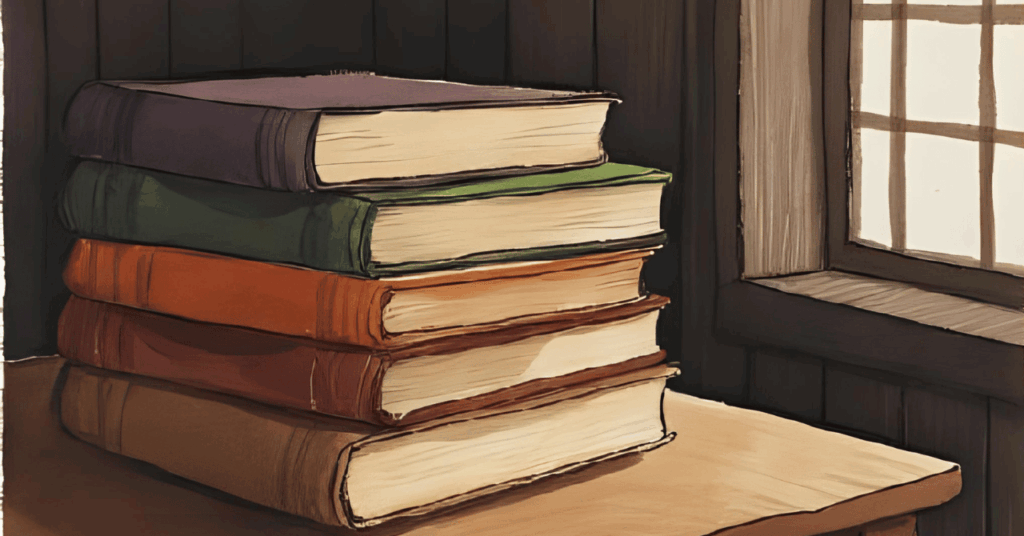
八木が読み聞かせしていた「どん底」という本は、1902年にロシアの作家マクシム・ゴーリキーが書いた有名な戯曲(演劇の台本)です。
詳しく見ていきましょう。
「どん底」のあらすじ
舞台は、ロシアの貧しい人たちが住む安宿です。
そこには、元貴族、元俳優、泥棒、娼婦など、人生に失敗した様々な人たちが集まって暮らしています。
みんな貧乏で、希望も失っている状態です。
ある日、「ルカ」という老人がやってきます。
ルカおじさんは住人たちに優しい言葉をかけ、「きっと良いことがある」「頑張れば報われる」と励まします。
住人たちは一時的に希望を持ちますが、やがてルカおじさんは去っていき、現実は何も変わっていないことに気づきます。
「どん底」の結末
「どん底」では、ルカおじさんがいなくなった後も、様々な悲劇が起こります。
住人たちは悲しみにくれながらも、また歌を歌い始めますが、貧乏で苦しい生活は続いていきます。
「どん底」の結末は、「希望を持つことは大切だが、現実はそう簡単に変わらない」という救いのない終わり方です。
しかし、同時に「人間の強さ・逞しさ」も描いた結末となっています。
描かれているテーマ
ゴーリキーのこの戯曲は、「人生のどん底にいる人たちの物語を通して、人間の生き方や社会について考えさせる作品」です。
具体的には、以下のようなテーマがあると考えられます。
- 貧困の中で生きる人々の苦しみ
- 希望を持つことの大切さと、同時にその難しさ
- 人間の尊厳について
- 社会の底辺で生きる人たちにも、それぞれの人生と価値があること
戯曲「どん底」は1902年にモスクワで初めて上演され、当時のロシア社会の問題を正面から描いた作品として高く評価されました。
当時のロシアは、社会への矛盾や問題が大きくなっていた時期であり、ゴーリキーのような作家たちが文学を通じて社会問題に訴えかけていたのです。
印象的な名言やセリフ
朝ドラ「あんぱん」では、かつての八木上等兵がこのようなセリフを読み聞かせしているシーンが描かれました。
 八木信之介(小倉連隊)
八木信之介(小倉連隊)”仕事が楽しみなら人生は極楽。だが、義務なら人生は地獄だ”
「どん底」の登場人物たちは皆、様々な理由で働くことができない、または働いても報われない状況にいます。
八木信之介が読み上げたこのセリフは、そうした境遇の中で「労働」や「生きること」について語られた哲学的な言葉です。
他にも、ゴーリキーの「どん底」には様々な名言やセリフがあります。
人間をいじめるな……
しかしもし一生涯起き上がることの出来ねえ程おれをいじめた 奴があったら、おれはどうするか、許すか。
なあに決して許さねえ。
人間とはいってえなんだ?
それはお前でもねえ、おれでもねえ、奴等でもねえ・・・みんなちがう!
それは、お前も、おれも、やつらも、爺さんも、ナポレオンも、マホメットも・・・
みんな一緒にしたものだ!
人間は尊敬すべきものだ。
憐れむものじゃない。
同情なんかで侮辱するものじゃない。
人間ってのは、いい方向に進むための道を探し求めているものなんじゃよ。
本に対する感想
実際に「どん底」という作品に触れた人からは、「読んだ後に虚無感に襲われる」「暗くて重い」という印象が多く聞こえてきます。
一方で、その救いようの無いストーリーに「ロシア文学らしい」「圧倒された」という声もありました。
主な感想や反応
ハッピーエンドとは程遠く、読後感も重いが、ロシア文学らしい容赦のなさが逆に印象に残る作品だった。
圧倒される。
貧民層のあらゆる人の生き様を熱く描かれ、作品の熱を感じた。
希望のない劇と言えるのですが、ルカのような人物がどこかにいるのではないかと思わせることで、単なるリアリズムを脱した作品です。
※読書メーターより引用
あんぱんで八木が「どん底」を読み聞かせした理由はなぜ?
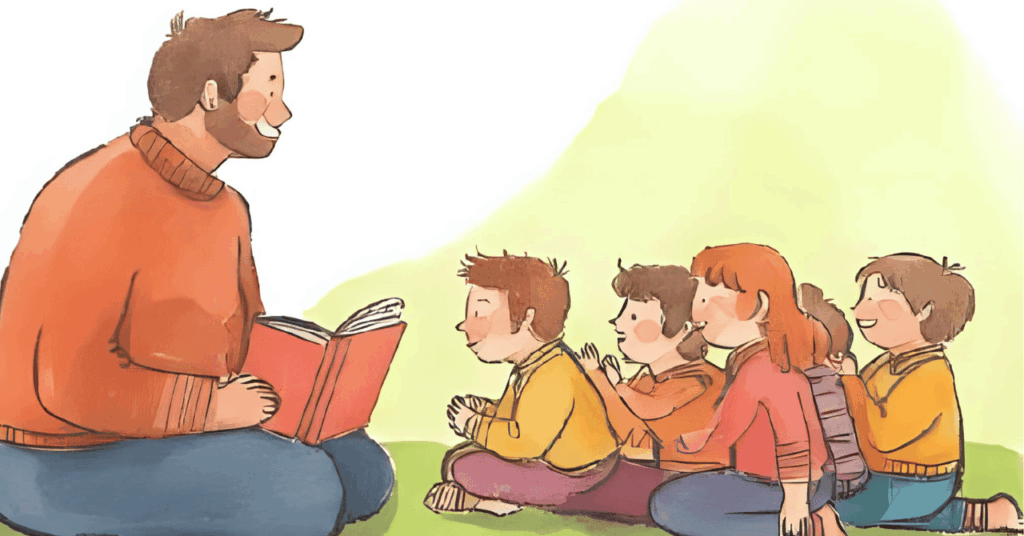
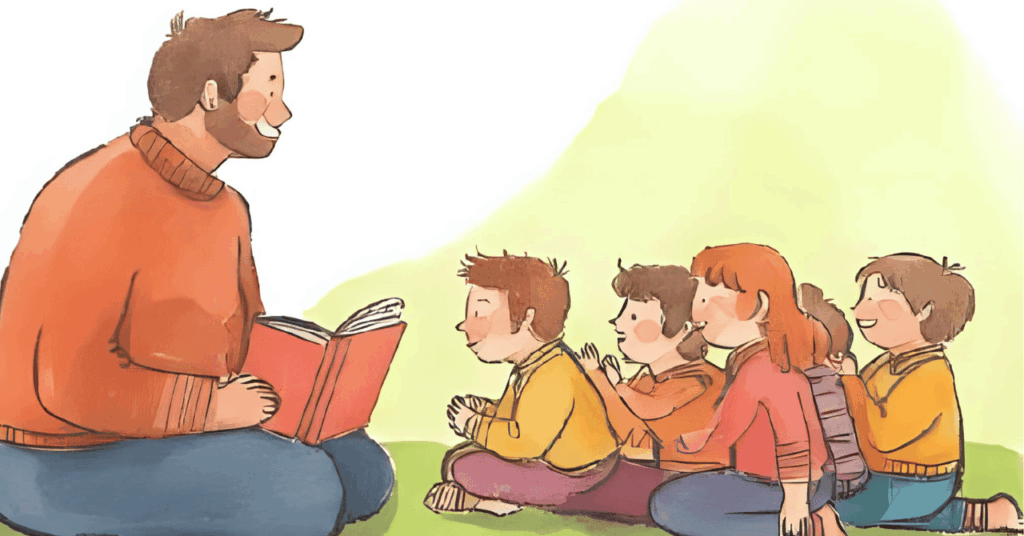
八木信之介のモデルとされるサンリオ創設者・辻信太郎氏が、感銘を受けた本としてゴーリキーの「どん底」が挙げられているためと考えられます。
モデルとの関係
妻夫木聡さん演じる「八木信之介」という人物は架空のキャラクターとされていますが、実際にはサンリオの創設者である辻信太郎さんとの関連があると噂されています。
#朝ドラあんぱん 八木上等兵は、やなせさんの戦友の上等兵の方と、もう1人、サンリオの創業者の辻さんという方がモチーフに組み合わせられているという記事を見て、辻信太郎さんを検索してみたら、御歳97歳でご存命!キティちゃんを抱える姿が、かわいらしい… #あんぱん pic.twitter.com/mWURz6KtSK
— YuiMac🏳️🌈Hakidame🏳️⚧️ (@yuimac1985) June 13, 2025
↓関連記事↓


辻信太郎さんは、やなせたかしさんの詩の才能を見抜き、「詩とメルヘン」という雑誌の発行に協力する強力な支援者となる存在です。
そんな辻信太郎さんは、八木と同様に「文学を愛する人」。
著書「これがサンリオの秘密です。」の中で、感銘を受けた作品として、
- マクシム・ゴーリキーの戯曲『どん底』
- アンドレ・ジッドの小説『狭き門』
- ジャン=ポール・サルトルの小説『壁』
などを挙げています。
そのため、八木信之介という人物を描く上で、影響を与えた作品を「あんぱん」の中でも取り上げた可能性が考えられます。
以前も、「井伏鱒二の詩集」という固有名詞が出てきたことがありましたね。
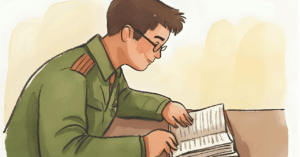
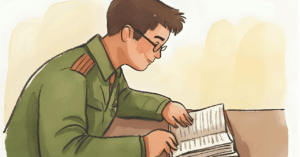
孤児に読み聞かせした理由
とはいえ、モデルとされる辻信太郎さんが「東京で孤児を助けていた」とか「闇酒を売っていた」という実話エピソードはなく、ドラマ上の架空のストーリーです。
「どん底」という暗い話を子供達に読み聞かせする八木を見て、嵩は「八木上等兵らしいな」と呟くシーンもありました。
八木はなぜ子供達にこのような暗い話を読み聞かせしたのでしょうか?
考えられる意図としては、
- 「世界には同じような境遇の人がいる」という共感や慰め
- 「どんなに貧しくても君たちは価値のある人間だ」という人間の尊厳を伝えるため
- 絶望的な状況でも希望を持ち続ける大切さを伝えるため
- 現実を直視しながら生きる強さを身につけるため
- 一緒に支え合うことの大切さを伝えるため
などがあると筆者は感じました。
一方で、そこまで深い意味はなく、単に「変わり者」という八木信之介の人物像を描く上で、このようなエピソードを入れてきた可能性も考えられます。
ネット上では「子供にどん底は不適切」「流石にヘビーすぎる」という声も挙がっていました。
八木先生、子どもたちにゴーリキーの「どん底」はヘビーすぎるだろ…
— さとひ/渡辺裕子(仕事用) (@satohi11) July 13, 2025
#朝ドラあんぱん
とはいえ、八木も子供たちも楽しそうに笑っていたので、あまり重くならないように配慮する優しさも感じられました。
【関連記事】




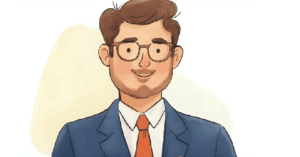
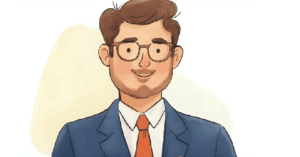

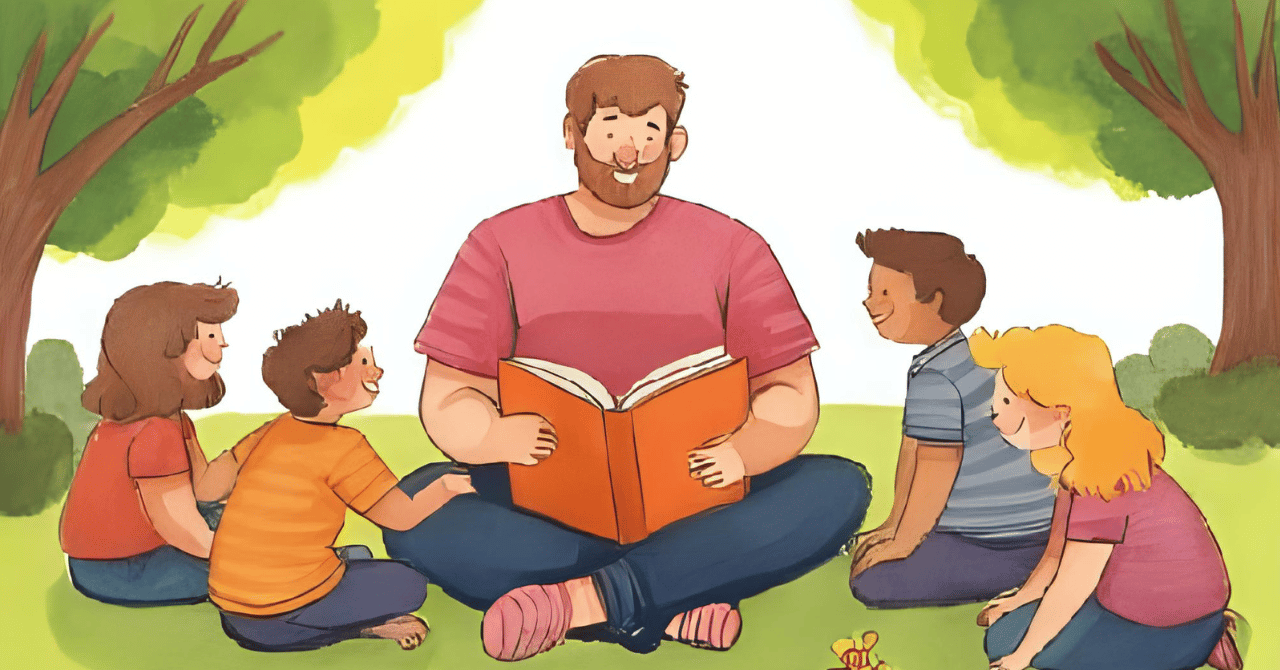










コメント