桜井ユキさん主演のNHKドラマ「しあわせは食べて寝て待て」。
その第5話で、副業を再開するか迷っているさとこがスーパーで手に取ったのは、「牡蠣(かき)」でした。
さとこは、牡蠣を海苔で巻いた料理を作り、美味しそうに食べていましたね。
そこで今回は、「牡蠣の海苔巻ソテーのレシピ・作り方」について詳しくご紹介していきます!
しあわせは食べて寝て待てレシピ:牡蠣の海苔巻の作り方は?
そこで今回は、「しあわせは食べて寝て待て」の牡蠣の海苔巻ソテーの”再現レシピ”をご紹介します!
ぜひ参考にしながら作ってみてくださいね。
牡蠣の海苔巻:用意するもの(2人分)
- むきみ牡蠣:8〜12個程度
- 海苔:1〜2枚
- 塩コショウ:適量
- 片栗粉:適量
- サラダ油:適量
- しょうゆ:適量
牡蠣の海苔巻:下ごしらえ
片栗粉は表面をカリっとさせたり、海苔との馴染みをよくしますが、省略してもOK。
牡蠣の海苔巻:焼き方
風味をもっと良くしたい時は油の代わりに「バター」もおすすめです。
醤油の香りを生かすために最後の仕上げがおすすめ。
ドラマでは、醤油をフライパン2周ほど回しかけていました。
焼いた後の牡蠣の汁も回しかけていただきましょう。
ドラマでは、牡蠣のソテーの付け合わせに「ホウレンソウのお浸し」のようなものが添えられていました。
薬膳的にみたホウレンソウには、血のめぐりを補い、エネルギーを補充する効果がありますし、彩りにもなりますね。
しあわせは食べて寝て待て:牡蠣の薬膳的な効能とは?
牡蠣と不安との関係
中医学では、不安・緊張・不眠などは「心(しん)」や「肝(かん)」の不調とされ、「心神不安(しんしんふあん)」という状態です。
牡蠣にはこの「心神」を安定させる安神作用があるため、不安が強いときや気分が落ち着かないときにとてもおすすめの食材とされています。
薬膳では牡蠣の殻(牡蛎殻・ぼれい)も漢方薬として使われ、強い安神作用があるとされます(専門処方が必要)。
牡蠣の薬膳的効能
| 効能 | 説明 |
|---|---|
| 安神(あんしん) | 心を鎮め、不安やイライラ、不眠を緩和する作用があります。特に「驚きやすい」「緊張しやすい」タイプの人におすすめ。 |
| 補腎(ほじん) | 腎の精(生命エネルギー)を補い、ホルモンバランスや性機能、骨や髪の健康をサポートします。 |
| 軟堅散結(なんけんさんけつ) | 固くなったしこりや腫れ(甲状腺腫、リンパ節の腫れなど)を和らげるとされます。 |
| 収斂作用(しゅうれん) | 体液の漏れを防ぐ作用があり、寝汗、遺精などに良いとされています。 |
主人公のさとこが持っている薬膳の本については、こちらの記事で紹介しています。

牡蠣を食べる時のポイント
身体を冷やす性質(寒性)があるため、冷え性の方や胃腸が弱い方は加熱して、温性の食材(生姜、ネギなど)と一緒に摂るのがおすすめです。
生食は避け、蒸したり、焼いたり、煮込んだりすると良いでしょう。
先ほどご紹介した「牡蠣の海苔巻ソテー」も体を冷やさずに牡蠣の効能をいただけるレシピですね!
一方で、食べ過ぎると体を冷やしたり、ミネラル過多(亜鉛や鉄)でバランスを崩す可能性があるので気をつけましょう。
週に1〜2回程度、1回当たり4〜6個くらい(加熱)を目安に。
まとめ
今回は、ドラマ「しあわせは食べて寝て待て」の第5話に登場した「牡蠣の海苔巻ソテー」の作り方・レシピについてご紹介しました。
醤油の香りが食欲をそそりそうな一品で、思わず作りたくなりますよね。
心がちょっと不安な時は、薬膳の知識を生かして乗り越えていきましょう。
なお、原作漫画では、第3巻に「牡蠣の海苔巻ソテー」が登場するそうです!
こちらの記事では、しあわせは食べて寝て待てのさつまいもの作り方についてご紹介しています。

さとこが持ち歩いている薬膳・食材ノートのモデルについてはこちらの記事をどうぞ。

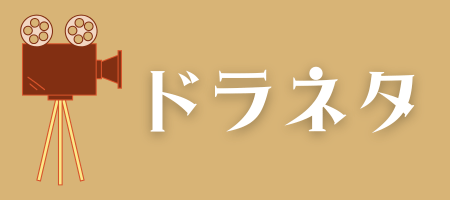
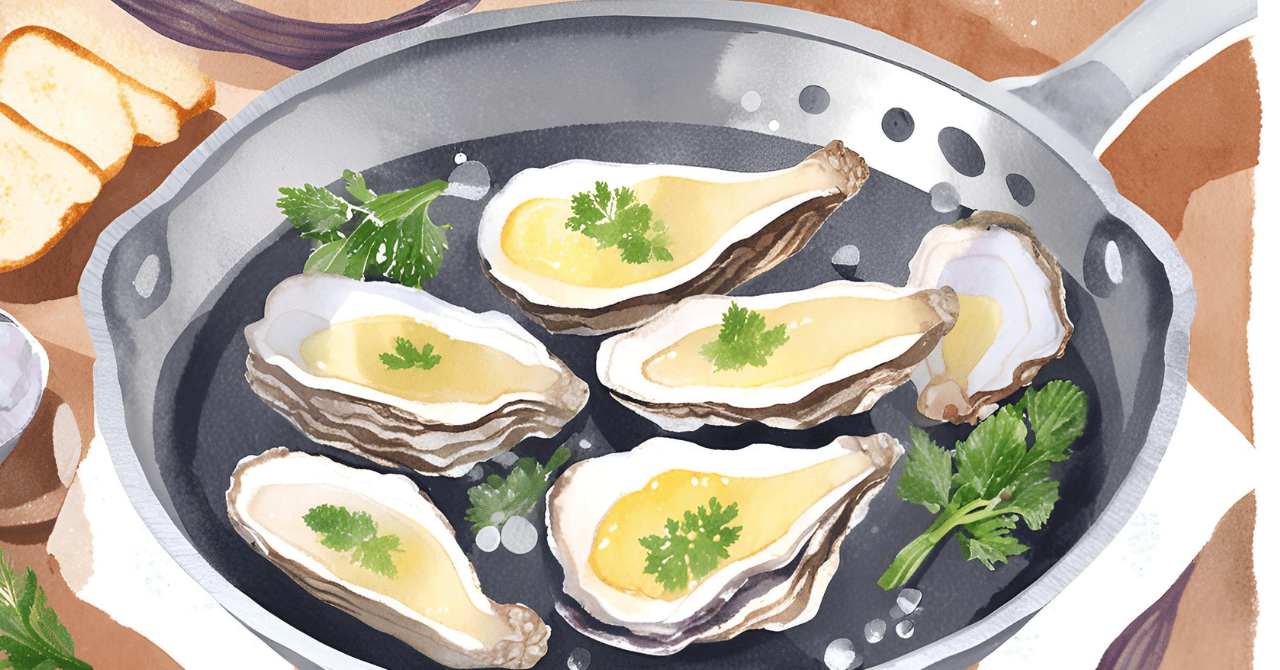





コメント